
『Victoria 3』の開発日記#154は、ナショナリズムの表現における改善点についてです。

次のアップデートやDLC「National Awakening」のテーマにもなるのニャ。
それでは見ていきましょう。前回の開発日記は以下のリンクから。
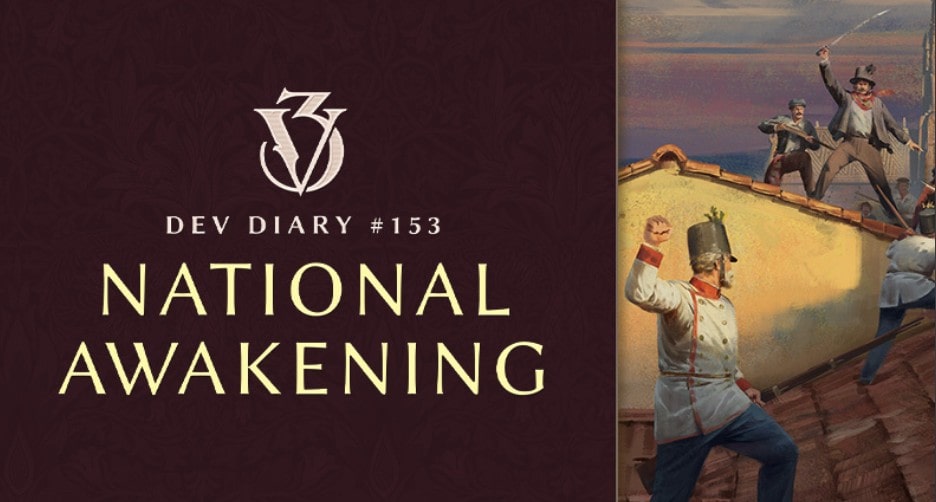
ナショナリズムの表現
こんにちは、木曜日おめでとうございます。Victoria 3のナラティブデザインリード、Victoriaです。今日は文化システムとナショナリズムの表現における改善点についてお話しします。
この日記では、市民権法、文化そのもの、そしてそれらにまつわる政治運動など、いくつかの興味深い分野を取り上げます。
この日記に掲載されている機能はすべて、無料アップデート1.10に含まれています。
序文
Victoria 3の設計者にとって永遠の不幸は、いつでも、何世紀にもわたる議論の渦中に巻き込まれるような仕事に直面する可能性があることです。
ナショナリズムというテーマに真剣に取り組もうとすれば、必然的に6つの難問に直面せざるを得なくなります。
ナショナリズムの台頭を許した条件は何だったのか?
ナショナリズムの特定の側面を想起させる数々の前近代的な現象をどう解釈するのか?
ナショナリズムが主張するその本質と、その本質をどう区別するのか?
なぜ前近代における地域的、宗教的、あるいは氏族的アイデンティティの混交が、いわゆる「国民的アイデンティティ」へと均質化してしまったのか?
「国家」とはどのように定義し、その定義から必然的に生じる曖昧さにどう対処するのか?
アップデート1.10におけるナショナリズムの描写においては、ゲームプレイ上の都合上、一定の抽象化と仮定を取り入れています。
これらのシステムを開発する際には、前述の疑問が頭をよぎりましたが、解決できたとは言えませんし、現実を可能な限り正確に再現できたとも言えません。
今回のアップデートで追加されたメカニクス要素は限定的で、「National Awakening(国家の覚醒)」というテーマを念頭に置いて開発されました。
開発にあたっては、帝国に懸念材料を与え、国民国家に地位向上のための手段を与えることを念頭に置いていました。
私たちの第二の目標は、文化運動全般の力強さを向上させ、ナショナリズムが世界における真の力であるように感じられるようにし、臣民と国民の区別を明確にすることです。
今回のアップデートでは、開発日記#152で紹介した「ナショナルプライド」機能を実装する予定はありません。
この機能は、十分な注意を払って対応できる後日のアップデートで実装すべきだと考えています。
臣民と国民
ナショナリズムとは一体何でしょうか?
ナショナリズムとは、国家は国民の政治的手段であるべきだというイデオロギーです。このように構成された国家は国民国家と呼ばれ、その政治的構成員は市民と呼ばれます。
国民国家は、オーストリア帝国が典型的な例である王朝国家と対比されることがあります。王朝国家とは、特定の国民の政治的代表としての役割ではなく、その統治王朝に正統性を与える国家です。
「ネイション」は非常に抽象的な概念であるため、定義するのがより困難です。
古代において、この言葉は一般的に共通の祖先と言語を持つ人々の集団を指し、現代的な「ネイション」の概念は18世紀後半から19世紀初頭にかけて出現しました。
19世紀のナショナリストが唱えた「ネイション」の定義は、血統、言語、血統といった人々に固有の特性によって定義される「客観的」概念から、共通の歴史と構成員の自発的な所属によって定義される「主観的」概念まで、多岐にわたりました。
これらの概念はしばしば「民族的」ナショナリズムと「市民的」ナショナリズムのモデルに分けられますが、当時のナショナリストは、その両方の要素を自らの言説に取り入れることが多かったのです。
「市民的ナショナリスト」として名高いフランスでさえ、平均的なナショナリストのイデオローグがアルジェリア人を真に同等のフランス人とみなす可能性は低いでしょう。
Victoria 3においては、ネイションは文化と同義であり、文化はポップの所有物です。
ポップが異なる文化に同化した場合、異なるネイションの一部になったと言えるでしょう。国民国家とは、特定の市民権法を有し、その国の主要文化を、その国が選出した構成員であるネイションと規定する国です。
オーストリアや清帝国のような王朝国家を表現するために、新たな法として「臣民性」を導入しました。
従属状態においては、Popの受容度は主にそのPopの居住地によって決まります。従属状態にある国は、あらゆる文化を持つPopが故郷に住んでいる場合、受容度を30増加させます。
さらに、故郷からの受容度にボーナスを与える「植民地問題なし」と組み合わせることで、この値を40まで引き上げることができます。
主権国家は、承認されていない大国や国民国家モデルを採用していない一部のヨーロッパ諸国にとって、新たなデフォルト法です。これは君主制と神政国家に限定されており、リベラルな利益団体や政治運動から強く反対されています。
主権国家は、国家の正統性が被統治者の同意ではなく、主権者から得られることを要求します。これはリベラリズムに反する概念です。
民族国家から多文化主義に至るまで、既存の市民権法は、市民権の多様な定義を反映するように再構築されました。
臣民性のない市民権法を有する国は、君主が国民の人格を体現する立場を主張する形であれ、民意に奉仕すると主張する代表者によって統治される共和国であれ、何らかの形で国民主権の原則を認めていると想定されます。
文化特性の再構築について解説する際に、刷新された市民権法についてより詳しく見ていきます。
文化的な熱狂
文化熱とは、ある文化における国民意識の度合いを測る指標です。
ベネディクト・アンダーソンの著書『想像の共同体』における国民概念に倣えば、ある文化を持つ人々が、その文化を持つすべての人々によって共有される共同体をどの程度想像しているかを測る指標となります。
文化熱が低い場合、彼らは特定の地域や、彼らが最も大切にしている他の識別子で自分を認識しようとするでしょう。
しかし、文化熱が高まるにつれて、彼らは地域的アイデンティティよりも国民意識を重視し、自らを国民の一員と呼ぶ傾向が強くなります。こうして、チロル人とバナト人は南ドイツ人となるのです。
文化的な熱狂 – 原因
熱意は様々な条件の影響を受けますが、それらは「熱意」という概念の中に分かりやすくまとめられています。すべての熱意の効果は、その文化のPopが何人いるかに基づいて適用されます。
例えば、南ドイツのPopの10%が民族国家を持つ南ドイツの国に居住し、90%が従属国を持つ国に住んでいる場合、南ドイツの文化は法律によって合計+2の熱意を得ます。識字率、ナショナリズム技術の影響などについても同様です。
これらの条件は、地方固有の文学文化の発展、壊滅的な紛争をめぐって生まれる国家神話、国の統一的な歴史を構築しようとする学者や国家官僚の努力、文化の「公式」表現を生み出す公立学校制度の役割といった傾向を抽象化するのに役立ちます。
これらの条件の多くは、特定の主要文化を持つ独立国家の存在に依存していることにも留意すべきです。明確な内集団と外集団を定義する排他的な国民国家は、文化が国家へと変容するための最も強力な手段です。
独立したばかりの国家は、自国の主要文化への熱意を急速に高め、国境の内外におけるナショナリズムに富んだ民衆の利益を享受するために、非常に制限的な市民権法を制定しようとするかもしれません。
同様に、特定の文化を持つ大勢の人々を鎮圧しようとする帝国は、その主要文化を持つ国が国内で分離主義を助長しないよう、常に監視するのが最善です。
より具体的な例を挙げましょう。多くのアイルランドの若者がアメリカに移住し、そこで読み書きができるようになり、大学に教員として採用されます。
こうしてアイルランド文化への熱意が高まり、イギリスではアイルランド国民の間で高まった熱意の影響、例えばポップカルチャーへの関心の高まりやアイルランド国民運動の活発化などが見られます。
文化的な熱狂 – 影響
文化の熱意は、ポップと国家の両方に影響を与えます。
高い文化熱意を持つポップは同化に抵抗し、多数派・少数派を問わず文化運動に参加する傾向が強くなります。
高い熱意を持つ文化を代表する文化的少数派運動は、その基本行動力にボーナスを与えます。さらに、運動に新たに追加された「頑固さ」機能と相まって、不満を抱く文化的少数派運動が国家に与える影響ははるかに大きくなります。
熱意の高い主要文化は、戦時において国家にとって恩恵となり、国内政治を国家主義的な方向に傾かせます。主要文化の文化熱意が高いと、戦争支持率の低下速度が低下し、非従属市民権法の下では自由欲求の獲得量も増加します。
高い文化熱を持つ一次文化のポップは、文化多数派運動に参加する傾向が強い。これは、彼らを厄介な反対派の政治運動から遠ざけ、彼らの利益団体に圧力をかけ、民族国家主義的な政治家の出現率を高めます。差別的な市民権法を維持することで、国民の特権階級を政治的に無力化することができます。
さらに、熱意の高い主要文化を持つAI国家は、領有権の獲得、君主からの独立、あるいはライバル国への屈辱を求める際に、より大胆かつ攻撃的になります。
国内においては、国家主義的な国内政治アジェンダを採用する傾向が強まります。
文化的特性の再構築
アップデート1.10では、各文化が持つ識別特性が標準化されました。
デフォルトでは、各文化は言語特性と伝統特性の2つの特性を持つようになりました。
これらの特性は、より大きな特性グループに含まれています。つまり、各文化は関連性の異なる4つの特性を持つようになり、それらは文化の近い親戚と遠い親戚を表しています。
文化は、文化間の伝統的なつながりを表す「伝統」特性を獲得したり失ったりすることもあります。これは受容度にボーナスをもたらします。
例えば、バルト・ドイツ人とヴォルガ・ドイツ人を表す新しい東ドイツ文化は、「ロシア圏」特性を持っています。この「ロシア圏」特性はロシア人、タタール人、その他多くの民族に共通しており、ロシアに住む東ドイツ人は、北ドイツや南ドイツに住む同胞よりもはるかに高い受容度を持つことになります。
宗教特性も同様の仕組みにアップデートされました。例えば、カトリックには、アブラハムの特性グループに属する「キリスト教」特性が追加されました。
この特性と特性グループというシステムにより、国教や国文化との近さに基づいて、法律が文化や宗教を段階的に差別することが可能になります。
市民権法と教会と国家に関する法律は、このより幅広い可能性を組み込むよう改正されました。一般的に、共通の特性を持つ文化は、共通の特性グループを持つ文化よりも受け入れられやすく、共通の特性グループを持つ文化は、全く共通点のない文化よりも受け入れられやすいのです。
動きの追加
アップデート1.10では、政治運動にいくつかの変更を加えました。特にアイデンティティに基づく運動に焦点を当てています。
これらの変更の目的は、アイデンティティに基づく運動が、多国籍帝国にとって重要な脅威となる強力なアクターとして感じられるようにすることです。
頑固さ
アップデート1.8の政治運動のリワーク以来、政治運動において受動性と反乱性の間に「中間」状態が存在しないという問題が根強く残っていました。この問題は特に文化運動に影響を及ぼします。
アップデート1.10では、文化運動と宗教運動に新たな中間状態「頑固さ」が加わります。
頑固さは、市民的不服従、そして特定地域における排除されたコミュニティ間の準国家構造の形成を表します。
頑固さは混乱とは異なります。特定の文化の急進派は活動主義に貢献するかもしれませんが、頑固さに貢献するためには必ずしも急進的である必要はありません。運動によって生み出される頑固さのレベルは、その支持者と結びついています。
つまり、特定の文化や宗教グループの中でも、政治的に最も進歩的な層が最初に頑固になる傾向があります。自らの利益を代表する政治運動を持たない文化は、完全に組織化された運動よりも権力を行使する能力がはるかに低くなります。
反乱を引き起こす文化的または宗教的な運動は、必然的に強情なものとなり、反乱に至る過程で国家を弱体化させます。
複数の動きが同時に起こると、頑固さが生じる可能性があります。ここでは、オーストリアはいくつかの誤った決定を下したにもかかわらず、チェコ、ポーランド、イタリアの国民運動から同時に頑固さを経験しています。
歴史的に見ると、オーストリア=ハンガリー帝国の妥協後から第一次世界大戦に至るまで、ボヘミア議会はチェコとドイツの民族主義政党間の対立によりしばしば膠着状態に陥り、準国家機関の台頭につながりました。
1913年に皇帝勅令によってボヘミア議会が解散されると、これらの準国家機関はオーストリアの政権よりも高い正統性を獲得し、最終的にチェコ国民委員会の手によってチェコは独立を果たしました。
ゲーム的に言えば、ボヘミアはドイツとチェコ双方の民族運動によって生み出された「頑固さ」によって統治不能な状態に陥りました。同様の現象がオーストリア=ハンガリー帝国の王領全域で繰り返され、帝国の崩壊へとつながりました。
運動の流出
アップデート1.10では、運動に国境を越えた影響を及ぼせるようになりました。ある運動が反乱運動化すると、近隣諸国にある同種の運動の活動レベルが上昇します。
例えば、ロシアのポーランド民族運動が反乱運動化すると、オーストリアとプロイセンのポーランド民族運動の活動レベルも上昇します。
この効果はイデオロギー運動にも適用されます。フランスの共産主義運動が反乱を起こした場合、ベルギー、スペイン、イタリア、ドイツの近隣諸国の共産主義運動は扇動をエスカレートさせます。
さらに、イデオロギー運動は、その創設条件が満たされ、かつプレステージの高い近隣国に同じ運動が存在する場合、発生する可能性が高まります。
その他の変更点
鋭い観察力を持つ方なら、上記の市民権法に新たな補正値「分離主義の強さを支持」と「分離主義への抵抗力を支持」が追加されていることに気付くでしょう。
これらの補正値は、新たに追加された外交行動「分離主義を支持」に関係します。
「分離主義支援」の相互作用は、ナショナリズムの研究によって解除され、対象国における文化的少数派運動の民衆の支持と積極性を高めます。この相互作用の強さは、開始国と対象国の威信の差、および「分離主義支援」の強さ/抵抗力の補正によって調整されます。
上記のように、民族国家は「分離主義支援」の強さにボーナスを得ますが、その一方で分離主義に対して脆弱です。
一方、多文化主義を採用している国は分離主義に対する耐性が強い一方で、分離主義を促進する能力は低くなります。
分離主義への対抗手段としては、運動を開始した国の外交官を追放したり、影響を受けた運動を抑圧したり、運動の活動を減らす法律を制定したりすることが考えられます。
本日の締めくくりとして、「国家価値の促進」布告を改良しました。この布告はナショナリズム技術の研究によって解除され、故郷に住むポップに主要文化への同化を強制する可能性があります。
まとめ
アップデート1.9と商業憲章には、相互運用性の高い機能がいくつか含まれていました。
各メカニズムが互いに影響し合うこの開発スタイルは、アップデート1.10のゲームプレイにおいても目指されました。市民権は熱意と差別化に繋がり、文化運動に繋がります。文化運動は頑固さを誘発したり、強力な分離の連鎖反応を引き起こしたりする可能性があります。
野心的な国民国家は、熱意を可能な限り高めようと努め、民族主義的な闘争を通じて大帝国に亀裂を生じさせます。
帝国は、市民的不服従や分離によって領土が分割されるのを避けるために、熱意を最小限に抑え、様々な民族をなだめるという慎重なバランス感覚を要求されます。
最後にもう 1 つ例を挙げましょう。オスマン帝国がセルビア保護領を戦争に巻き込み、セルビア人の民衆に多くの犠牲者を出しました。
これらの犠牲者とセルビア国家による民衆の教育努力が相まってセルビア人の熱意が高まり、オスマン帝国とセルビア双方のセルビア人の民衆が文化運動に参加し、セルビアの自由への欲求が高まりました。
セルビアが高まった自由への欲求に基づいて行動し、オスマン帝国に対して独立戦争を開始した場合、戦争支持の減少が少なくなるという恩恵を受けるでしょう。
自由への欲求を高めてから戦争を開始するまでの間に、セルビアは分離主義の支援アクションを使用して、オスマン帝国におけるセルビア国民運動の積極的行動と民衆の魅力をさらに高めることもできます。
その結果、オスマン帝国の領土に頑固さを生み出したり、分離独立を引き起こしたりして、オスマン帝国が活用できる立場になる可能性があります。



