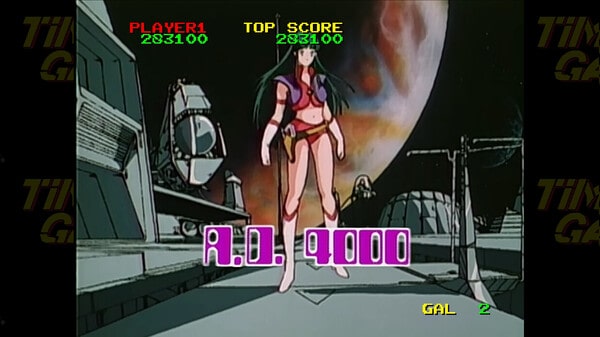前回はSteamのおすすめデッキ構築ローグライトでしたが、今回は「Steamで遊べるおすすめボードゲーム」です。
前回もちょっとマイナーなローグライトが中心になっていましたが、今回も一般的にはちょっとマイナーだけど面白いボードゲームが中心になっています。そのため『ウイングスパン』や『Scythe』『タリスマン』『カタン』『ドミニオン』といった、何度も紹介している有名作品は省かせていただきました。

『UNO』とか『モノポリー』も出てこないのニャ。
それでは見ていきましょう!気になる作品があったら追加していきます。
Steamで遊べるおすすめボードゲーム!
*タイトル名をクリックするとストアページにとびます。
1:クランク!(Clank!)(3,249円)
プレイヤーはドラゴンに気づかれないよう城に忍び込み、アーティファクトを手に入れて地上に戻るという内容。それぞれのプレイヤーにはカードが配られ、それを駆使して場内を進んでいくというデッキ構築要素もあります。
タイトルの「Clank!」は物音で、行動に際して物音を立てるとドラゴンを怒らせてしまい、全員に対してブレスがとんできます。ブレスをくらうとHPが減り、0になった時点でそのプレイヤーは脱落。ゲームが進めば進むほど、ブレスは当たりやすくなります。
深く潜れば潜るほど獲得できるアーティファクトの点数が高くなりますが、そのぶん危険度も増します。どこまで行くのか、どこで引き返すのかなど、引き際の判断が求められるでしょう。
2:覇王龍城(Dragon Castle)(930円)
崩れ落ちる城から資材を取り、それを使って自分の城を建てていくというコンセプトのゲーム。『上海』のように同じ絵柄の麻雀パイ(っぽいもの)をとり、それを自分の盤面に配置します。盤面におなじ色の牌が4つ以上並んだら、裏返して城の土台となり、点数が入ります。
高いところで土台にした牌ほど点数が高くなります(1段目1点、2段目2点、3段目3点)。できるだけ高く積み上げるか、それとも早めに点数を取りに行くかのジレンマがあり、繰り返しプレイしたくなる作品です。
3:デューン 砂の惑星:インペリウム(Dune: Imperium)(2,576円)
小説や映画で人気の『デューン 砂の惑星』をボードゲームにした作品。デッキ構築とワーカープレイスを合わせた作品になっています。
内容はけっこう複雑で、資源を獲得しつつ、中立勢力とも仲良くしつつ、さらにターンの終わりでの戦争にもできるだけ勝たなければなりません。これを限られたワーカーを駆使してやらなければならないので、どこにどれだけ配置するかで頭を悩ませることになるでしょう。
4:こねこばくはつ2(Exploding Kittens 2)(2,050円)
『UNO』っぽいパーティカードゲーム。Steamにあるのは2ですが、ルールは1とおなじです。
プレイヤーには手札が規定数配られ、残りの山札を自分のターンに1枚ずつ引いていきます。ただし山札の中には「プレイヤー人数-1枚」のこねこばくはつカード(子猫がうっかり爆弾を爆発させてしまうという設定)が入っています。これを引いたプレイヤーは即ゲームオーバー。その場でゲームから排除されます。最後まで残ったプレイヤーの勝ちという単純明快なルールです。

いきなりこねこばくはつを引いてしまったら、もう遊べないのかニャ?
それぞれのプレイヤーは、爆弾解除カードを1枚だけ持っていますので、1回ひいただけならセーフです。また、自分の手番をスキップするカード、山札の上から3枚を見るカード、山札をシャッフルするカードなどもあり、カードを駆使していかに子猫をひかないようにするかが勝利のカギになります。それでも運用素が強いですけどね。
5:マンチキン(Munchkin)( 1,520円)
テーブルトークRPG(TRPG)を題材にしたカード使用のボードゲーム。プレイヤーは登場キャラクターの一人となり、仲間を出し抜いて武器や防具を手に入れてキャラクターを強化し、先にレベルを10まで上げたものの勝ちという内容です。タイトルの「マンチキン」というのはTRPGでいかさまをするプレイヤーのことだそうです。
敵と戦う時には仲間に協力してもいいですし(ただし勝ったときの報酬を山分け)、カードをつかって敵側の戦闘力を上げてもいいなど、適切なタイミングで仲間を蹴落とすこともできます。「友情崩壊ゲーム」ともいわれていますね。
6:One Deck Galaxy(1,500円)
一人用ボードゲーム『One Deck Dungeon』の宇宙版。ただ内容は大幅に複雑化しています。ダイスを振って、それを盤面上に配置していくことで解決するというルールは前作とおなじですが、単純に敵を倒すというものではなく、プレイヤーは複数の文明から一つを選び、星系を探査・発展させながら、宇宙の宿敵(アドバーサリー)に対抗することが目的することが目的となっています。

なんだか4Xのような壮大な内容になってしまったのニャ。
設定的には4Xゲームっぽいですね。ゲーム開始前に覚えることがとにかく多く、前作『One Deck Dungeon』をプレイしている方でもチュートリアルで挫折する可能性があります。前作をプレイしていなければ、まず前作からがおすすめです。
7:ウェルカム トゥ エバーデール(Welcome To Everdell)(1,700円)
ワーカープレイス作品のヒット作『エバーデール』を、サイコロを無しにしてカードだけでルールを簡略化したもの。子供向けの『マイリトル エバーデール』よりは複雑です。
1プレイが短時間で済むことから、筆者的には本作のほうが好きだったりします。簡略とはいえ、コンボによるスコアなど、オリジナルのおもしろさはしっかり顕在しています。さくっと『エバーデール』を遊びたい方にはちょうどいい作品です。
8:みんなと街コロ(3,000円)
人気の国産ボードゲーム『街コロ』と『街コロ通』がプレイできる作品。サイコロを振って得たお金で物件を獲得しつつ、拡大再生産しながら、最終的に目標の4つの物件(ランドマーク)を全部獲得できたプレイヤーの勝ち。
ただしランドマークは高額なので、他の物件を買いあさって収入を増やしていかないとなりません。他のプレイヤーからお金を奪える物件や、他のプレイヤーのターンでも収入が得られる物件などもあり、うまく組み合わせて収益を上げていきましょう。オンラインプレイにも対応しています。
9:ブルゴーニュ(The Castles of Burgundy)(1,520円)
プレイヤーは中世のフランス・ブルゴーニュ地方の領主として、自分の領地にタイルを配置して発展させ、最終的にもっとも多くの勝利点を獲得することを目指します。
各プレイヤーは毎ターン2個のダイスを振り、その出目を使ってアクションを行います。アクションは、タイル獲得、タイル配置、商品出荷、労働者2人獲得があります。得点の方法ですが、出荷や同色エリアをすべて埋めたりなどで稼いでいきます。重めのゲームですが、チュートリアルがありますし、ぐぐればルール紹介もあるので問題無く楽しめると思います。
10:チャーターストーン(Charterstone)(2,900円)
Jamey Stegmaier氏によってデザインされたレガシー型の村づくりボードゲーム。プレイヤーごとに「チャーター(領地)」が割り当てられ、それぞれが施設を建て、資源を集め、住民を増やしていく中で、ゲームボードそのものが少しずつ変化し、物語とゲームルールが進化していくのが大きな特徴です。
キャンペーン型(全12ゲーム)のレガシーゲームで、プレイを重ねることで新しいルールやカード、建物、物語の展開が次々に開放されていきます。実物の場合、ゲームボードには実際にシールを貼っていくため、一度遊ぶと「自分だけの村」が完成し、キャンペーン終了後も完成したボードで通常のゲームとして遊ぶことができます。
11:ワイナリーの四季(Viticulture)(1,520円)
イタリアのトスカーナ地方を舞台に、ワイン農園の運営をテーマにしたワーカープレイスメント型ボードゲーム。デザイナーは『チャーターストーン』とおなじくJamey Stegmaier氏です。
プレイヤーは家族から受け継いだワイナリーのオーナーとなり、ブドウの栽培からワインの醸造、そして出荷に至るまでの工程を管理しながら、最も繁栄したワイナリーを目指します。季節ごとに行動が変わるというユニークな構造で、春~冬の4シーズンを通じて労働者(ワーカー)を配置し、さまざまなアクションを実行して勝利点を得ていきます。一番勝利点の多いプレイヤーの勝ちとなります。何度も繰り返しプレイしたくなる魅力があります。
12:ふたつの城の物語(Between Two Castles)(1,320円)
タイルドラフト+共同建築を組み合わせた協力半分・競争半分のユニークなボードゲーム。プレイヤーたちは、両隣のプレイヤーとそれぞれ2つの城を共同で建築します。自分の城は1つではなく、「左右の隣人と1つずつ協力して2つの城を作る」のが最大の特徴です。
各ラウンド、タイルをドラフトして選びます。タイルには部屋の種類(寝室、食堂、庭、金庫など)があり、種類や配置に応じて得点条件が変わります。ゲーム終了時、自分が関わった2つの城のうち、点数の低い方が自分のスコアになります。つまり、「両方の城をバランスよく作らないと勝てない」ジレンマが面白さの核になっています。
13:ドリームホーム(Dream Home)(利用不可)
自分だけの理想の家を建てていくカード配置型ファミリーボードゲーム。プレイヤーは2階建て+屋根のマイホームをテーマに、リビング、寝室、バスルーム、書斎などを好きな場所に配置していきます。
ゲームは12ラウンドで、毎ラウンド、「部屋カード」と「機能カード」(家具や設備など)を1列で選び、自分の家に配置します。部屋は左から右へ、下の階から上の階へと順に作っていく必要があります。連結ボーナスなど、配置の仕方によって得点が変わるため、先のラウンドを見越した配置戦略がカギになるでしょう。
建てた部屋のバランスや機能性、インテリア、屋根の美しさなどが得点となり、もっとも快適で美しい家を作ったプレイヤーが勝利です。
14:ロレンツォ・イル・マニーフィコ(Lorenzo il Magnifico)(1,520円)
プレイヤーはルネサンス期のイタリア・フィレンツェの有力な貴族となり、建築・信仰・軍事・芸術などを発展させ、自らの家系を栄えさせていくことを目指します。基本はワーカープレイス+ダイス変動制のゲームで、資源管理・カードエンジン構築・得点獲得方法が多彩な、重量級ユーロゲームです。
ゲームは全6ラウンド。各ラウンドでは「建物」「人物」「領地」「冒険」などのカード(開発カード)を獲得していきます。プレイヤーは4つの労働者コマ(3つはダイスに依存、1つは無色)を使ってアクションを行います。アクションの強さがダイス目に依存するということですね。
各2ラウンドごとに「信仰チェック」があり、信仰ポイントが足りないとペナルティ(追放)を受けます。これを避けるか、あえて無視するかのジレンマがありますね。多様な点数の取り方があるので、じっくり遊ぶ人向きです。
15:黄河と長江(Yellow & Yangtze)(1,520円)
Reiner Knizia氏による『チグリス・ユーフラテス(Tigris & Euphrates)』の精神的続編。古代中国・戦国時代の群雄割拠をテーマにした戦略的タイル配置ゲームです。プレイヤーは中国に君臨する王朝のリーダーとなり、さまざまな勢力(軍事・農業・商業・文化・行政)をバランスよく発展させていきます。
各プレイヤーは5色(赤・青・緑・黒・黄)のリーダー駒を持ち、王国(勢力)を作っていきます。王国同士が接触すると戦闘が発生。各色のタイルを置いたり、戦争に勝ったりすると、その色の得点を獲得できますが、元になっている『チグリス・ユーフラテス』と同じく、「自分の最も低い色の得点が最終得点になる」という、独特で悩ましいルールが特徴です。バランスよく配置していきましょう。
16:スペース・フード・トラック(Space Food Truck)(980円)
宇宙を旅するフードトラックのクルーとなり、銀河中の注文に応えるという、バカバカしくも愛すべきテーマの協力型デッキ構築ボードゲーム。プレイヤーたちはそれぞれ1つの役職(キャプテン、シェフ、サイエンティスト、エンジニア)を受け持ち、宇宙を飛び回りながら、注文された料理を作り、届けていくのが目的です。
ゲームの流れですが、宇宙を探索し、各星で注文をうけ、材料を仕入れ、料理を完成させ、目的の星へ配達します。船はトラブルまみれなので、それに対処していかなくてはなりません。注文をすべて時間内に達成できれば勝利ですが、船が壊れたり、カード切れやクルー全員が行動不能になると敗北となります。コメディ色の強い作品です。
17:スピリット・アイランド(Spirit Island)(2,800円)
プレイヤーは島の精霊(スピリット)となり、侵略者から島を守るというテーマの協力型ボードゲームです。プレイヤーたちは力を合わせて侵略者を撃退し、島を守りながら自然と精霊の力を強化していきます。難易度が高めで、戦略的な思考が求められます。
各ターンで侵略者は島を進行し、土地を汚染したり、住民を配置したりします。進行が早いと、島が急速に破壊されてしまうため、早めの対策が重要。精霊ごとに異なる能力があり、これらを効果的に活用し、他のプレイヤーと連携して侵略者を駆逐していきましょう。すべての侵略者を排除し、島が完全に浄化されることで勝利です。
18:アイル・オブ・スカイ: 族長から王へ(Isle of Skye)(800円)
タイル配置と経済戦略を組み合わせた中量級ボードゲーム。スコットランドの美しい島「スカイ島」を舞台に、プレイヤーは部族の族長となって、自分の領地をタイルで拡張しながら、ゲームごとに異なる得点条件を満たします。最も多くの勝利点を獲得したプレイヤーが勝利。
各プレイヤーは3枚のタイルを引き、1枚は破棄、残り2枚は他のプレイヤーに売りに出します。他のプレイヤーがタイルを購入するか選び、買われたらお金が手に入ります。
買わなかった場合は、自分でその価格を銀行に支払って買い取らなければなりません。
タイルは道・牧草地・山・湖など、地形をつなげて配置する必要があります。得点条件に合わせた配置が必要なため、タイルの選び方・置き方が非常に重要になります。
19:ボーナンザ デュエル(Bohnanza The Duel)(410円)
人気ボードゲーム『ボーナンザ』シリーズの2人専用スピンオフ作品。基本ルールをベースにしつつ、交渉・豆の栽培・収穫・得点化の楽しさはそのままに、2人でも駆け引きが楽しめるようにアレンジされています。

『アグリコラ』と『アグリコラ 牧場の動物たち』(フタリコラ)みたいな感じなのニャ。
プレイヤーは毎ターン、手札の先頭から1〜2枚を自分の畑に植えます(強制)。畑は3つで、種類の異なる豆を種類別に栽培します。相手に豆を送ることができますが、断られれば自分で処理しないといけません。注文カードに対応した豆を収穫して、その条件を満たすと得点できます。より多くの注文カード(得点)を達成した方の勝利です。豆の送り合い(押し付け合い)が楽しい作品です。
20:フラッシュポイント 火災救助隊(Flash Point: Fire Rescue)(1,980円)
プレイヤー全員が消防士となり、協力して火災現場から人命を救出する協力型ボードゲームです。火が建物中に燃え広がる前に、7人以上の要救助者を救出できればプレイヤー全員の勝利。逆に、建物の損壊や犠牲者の数が一定に達すると全員敗北になります。
各ターン、AP(アクションポイント)を消費して行動します。消防士にはそれぞれ固有能力があり、うまくつかっていかなくてはなりません。そののち火災フェーズでサイコロを振り、火の発生源を決めます。火の勢いが増すたびに状況が悪化していくなか、時間と資源を使ってどれだけ多くの人(とペット)を助け出せるかがカギとなります。
21:ポーション・エクスプロージョン(Potion Explosion)(720円)
魔法学校の生徒となってポーション作りに励むパズル系ボードゲーム。『ぷよぷよ』などのような落ち物パズルゲームをボードゲームに落とし込んだような内容ですね。
ゲームの流れですが、自分の手番になったら材料を1個選んで取ります。同色の材料がぶつかると爆発(エクスプロージョン)して、さらに取れます。この流れが落ち物パズルゲームの連鎖のようになっています。手に入れた材料をつかってポーションをつくり、勝利点を得ます。一番勝利点の多いプレイヤーの勝利となります。
22:ジェム・ラッシュ(1,200円)
プレイヤーが魔法の鉱山で宝石を集め、建築を進めていくダンジョン探索系のボードゲーム。タイルをめくってダンジョンを拡張し、宝石を使って部屋を建設とポイントを稼いでいきます。
各プレイヤーは鉱山の入り口からスタート。部屋タイルを探索・追加しながらダンジョンを広げていきます。宝石を集め、部屋を建築して得点を獲得していき、誰かが所定の勝利点に達したらゲーム終了となります。気軽に遊べる戦略ゲームです。
23:スマッシュアップ(Smash Up)(800円)
2つの異なる勢力デッキを選んでシャッフルし、拠点を巡って争う、デッキ混成型の対戦カードゲーム。忍者と恐竜、ゾンビと魔法使い、海賊と宇宙人など、戦略とドタバタの両方を楽しめるのが魅力です。
プレイヤーはそれぞれ勢力を2つ選び、自分のデッキを作ります。各プレイヤーは自分のターンにミニオンカード(拠点に出す)、アクションカード(効果を発動) をそれぞれ1枚ずつプレイ。拠点のパワーが一定を超えたらブレイクし、そこにいたミニオンの強さに応じて得点が得られます。いち早く15点を獲得したプレイヤーが勝利。勢力同士のコンボが楽しい作品です。
24:北海の略奪者(Raiders of the North Sea)(1,520円)
バイキングとなって北海の村や砦、修道院を襲撃し、栄光と名誉を競うワーカープレイスメント型ゲーム。資源を集め、クルーを雇い、船で略奪に出かけて勝利点を得るという世紀末な内容ですね。

ヒャッハーなのニャ。
プレイヤーは毎ターン「ワーカーを1つ置き」「すでにあるワーカーを1つ取る」ことで2つのアクションを行います。村では資源(銀貨・家畜・鉄など)を得たり、クルーを雇ったりし、海上・北部では襲撃に出かけ、報酬と勝利点を獲得します。これらをバランスよくやっていくことが重要となります。
25:通路(Tsuro)(950円)
昔あった「チクタクバンバン」をボードゲームに落としこんだような内容。プレイヤーの駒はタイル状に描かれているレールに沿って動いていきますので、自分の駒が盤面から落ちないよう、また逆に敵の駒を盤面から落とすようにタイルを配置していきます。思いもよらない形で駒が落ちてしまったりなど、パーティゲームとしてはなかなか楽しめます。
26:サグラダ(Sagrada)(1,010円)
グラダ・ファミリアのステンドグラスをモチーフにしたダイス配置ボードゲームです。
プレイヤーは、制限のあるパネル(ステンドグラス)にダイスをうまく配置して、
得点条件を満たしながら最も美しい窓(高得点)を完成させることを目指します。
各プレイヤーは自分の「ステンドグラスボード」と難易度の異なる「窓カード」を選択。毎ラウンド、共通のダイスプールからドラフト形式で順番にダイスを取り、窓にはめ込んでいきます。
ダイスの配置には2つの制約あり、同じ色・同じ数字が隣接してはいけない(タテヨコ方向)、窓カードの「色指定」「数字指定」のマスにはそれに従うがあります。全10ラウンド後、得点計算をおこなって勝者を決めます。透明なカラーダイスが窓にキラキラ並ぶビジュアルが秀逸です。
27:ヘレティック・オペラティヴ(Heretic Operative)(2,050円)
ダークファンタジー世界で秘密結社の異端工作員(Heretic Operative)として活動し、迫り来る災厄や魔法の暴走を防ぐ協力型ストーリーボードゲーム。プレイヤーたちはそれぞれ独自の能力を持つ「異端者」となり、教会や国家に迫害されながらも、人類を守るためにあえて禁忌の魔法を使い、災厄を未然に防ぐという内容です。
シナリオ(全6種)とキャラクターを選択し、ダイスロールとアクションで協力して危機に対処していきます。イベントカードで毎ターン発生する世界の変化や災厄に対処していかなくてはなりません。シナリオ目標をクリアすれば勝利です。『パンデミック』などシナリオ型ボードゲームが好きな人におすすめです。
28:ズーロレット(Zoolorret)(販売中止)
プレイヤーは動物園の園長となって、さまざまな動物を集めながら、魅力的な動物園を完成させることを目指すファミリー向けのボードゲーム。自分の動物園に同じ種類の動物をまとめて配置したり、赤ちゃん動物を誕生させたり、屋台を設置して収益を得たりして、最も多くの勝利点を集めたプレイヤーの勝利となります。
毎ラウンド、プレイヤーは山札から動物や屋台のタイルを引いて、「配送トラック」と呼ばれる列に配置していきます。トラックには3枚までタイルを積めます。トラックで得た動物や屋台を自分の動物園ボードに配置しますが、一つの檻におなじ種類の動物しか入れられないので注意。各檻に収まった動物の種類と数に応じて得点されます。家族で気楽に楽しめる内容です。
29:フォックス・イン・ザ・フォレスト(The Fox in the Forest)(720円)
2人専用のトリックテイキングカードゲーム。13回の「トリック(勝負)」を行い、ちょうど良い数の勝利を収めることで得点を稼ぎ、数ラウンド後に合計得点が高い方が勝利。ただし勝ちすぎると点数が下がるというジレンマがあります。
ゲームルールは簡単で、3種類のスート(色)の1〜11の数字カードが配られます。先攻が1枚カードを出し、もう一人が同じスートを出します。このときに数字の大きい方の勝ち。一部のカード(3・5・7・9)は「特殊効果」があり、トリックを変化させます。これを13回繰り返し、勝った回数によって点数が決まります。ただし10〜13回(ゲームルールによって変化)勝ってしまうと0点になるなど、勝ち過ぎた場合は点数をもらえません。これをどうやって調整するかが重要になってきます。
30:フォート・サムター(Fort Sumter)(820円)
アメリカ南北戦争勃発直前の政治的対立をテーマにした、2人用のカードドリブン戦略ゲーム。1860~61年の「南部分離の危機(Secession Crisis)」を舞台に、「連邦派(Unionist)」 と「分離派(Secessionist)」のいずれかの陣営を担当し、政治・軍事・世論など各エリアで影響力を競います。3ラウンド+最終クライシスでゲームが進行し、影響力の合計で勝敗が決まります。
盤面は、政治圏(Political spaces)、公衆世論(Public Opinion)、危機圏(Crisis Track)、軍事的緊張(Military track)で構成されています。各エリアに影響力キューブを配置・操作し、自分の陣営が優勢となるよう争います。
流れとしては、戦略カード(Strategy Cards) を使用して、自分の影響力を盤面に配置・移動。カードには「イベント効果」か「OPS値(影響力操作)」があり、どちらかを選んで使用します。
各ラウンドの最後に「危機カード(Crisis Card)」で点数計算。最終ラウンドでは「秘密目的(Secret Objective)」の達成も勝敗に影響します。最後にすべてのエリアを再評価し、最終的な勝利者を決定するという内容です。『トワイライト・ストラグル』的な戦略ゲームが好きな方には合うと思います。
31:ギャラクシー・トラッカー(Galaxy Trucker)(1,010円)
宇宙トラックの運転手として、ガラクタから即席で宇宙船を組み立て、宇宙の危険な航路を貨物を運びながら走破するというパーティー系SFボードゲーム。
プレイヤーは中央に裏向きに置かれた「宇宙船パーツ(タイル)」を一斉に取り合い、それで宇宙船を組み立てていきます。そしてこの宇宙船をつかって、イベントカードを順にめくりながら航行していきますが、「隕石衝突」「海賊の襲撃」「宇宙疫病」といったイベントが目白押しで宇宙船が壊れていきます。
旅の間に集めた貨物や、船体の無傷具合などに応じてお金(勝利点)を獲得。最終的に最も多くのお金を稼いだプレイヤーが勝利となります。
32:ブラッド・レイジ(Blood Rage)(2,300円)
北欧神話とヴァイキングをテーマにした壮大な戦闘と戦略を楽しめるボードゲーム。プレイヤーはヴァイキング一族を率いて、戦闘、領土拡張、神々の力を駆使し、最終的にラグナロク(終末の日)を迎える前に最も多くの名誉(勝利点)を獲得することを目指します。
ゲームは3ラウンドに分かれており、各ラウンドは「戦士の雇用」→「領土拡大」をおこないます。最終ラウンドでラグナロクが発生。死んだヴァイキングは最終的にポイントを得るチャンスとして重要です。最も多くの名誉を得たプレイヤーが勝者となります。イラストも美しく、なかなか遊べる作品です。
33:スルー・ジ・エイジズ(Through the Ages)(1,640円)
簡単にいうと「シヴィライゼーション」シリーズをボードゲームにしたような内容。古代から現代までの時代の間に、プレイヤーは自分の文明を発展させ、他のプレイヤーと競いながら最も高い文明ポイント(勝利点)を目指します。
アクションフェイズでは、カードをプレイして文明を発展させます。カードには技術、人物、政府、軍事、資源など、さまざまな効果を持つものがあります。またリソース(食料、鉱物、金)を使って建物やユニットを建設し、科学的な進歩を目指します。
戦争の要素もあり、戦争カードを利用して他のプレイヤーの文明に戦争を仕掛けたり、逆に自文明を守ったりすることが求められます。短時間で「シヴィライゼーション」的なゲームをプレイしたい人には最適です。
34:キャリコ ~陽だまりネコとパッチワーク~(Quilts and Cats of Calico)(2,198円)
ヘクスタイル型のパッチワークをボードに配置していき、猫が好むような素敵なキルトを完成させるパズル要素のあるボードゲーム。

猫ゲームなのニャ。
パッチワークには色と模様の違いがあり、目標タイルの条件通りに配置していくことで得点がもらえます。例えば目標タイルに「AA-BB-CC」と書かれていた場合、そのまわりに色もしくは模様がおなじものを3組つくるということですね。これ以外にも、おなじ色を3つつなげたり、猫の好きな模様の組み合わせをつなげたりで、得点をとっていくことができます。
ボードが狭いので、置き方はけっこう頭をつかいます。パズルゲーム好きな人にもおすすめですね。
35:アイル・オブ・キャッツ(The Isle of Cats)(1,700円)
猫ゲームその2。「闇の手」の異名を持つヴェッシュの軍勢が迫る前に、島の猫を救出し、船に乗せて脱出しなければならないというぶっとんだストーリー。

猫を助けるゲームニャ。
猫にはいろいろな形があり、テトリスのように船に敷き詰めて配置しなければならない。こちらもパズルゲームの要素があります。最初に配れるカードに書かれた条件を満たしたり、同じ色の猫をつなげたりで得点をとっていきます。ネズミが船内に残っていると減点など、一手一手ちゃんと考えて行動していく必要があります。
36:K2(2,170円)
K2に挑む登山ゲーム(K2以外もあり)。プレイヤーは2人の登山家をあやつり、できるだけ高いところまで登ることでスコアをゲットできる(高いところでとどまる必要はなく、一番高いところがスコアになる)。18ラウンド後に登山家2人の合計点を足して、一番スコアの高いプレイヤーの勝ち。
登山家には順応度という名前のHPがあって、これが0になると死亡。どれだけ高くのぼっても1点になってしまうので、どこらへんで妥協するかも勝負どころです。天候の要素もあり、天候が悪いと順応度のマイナスも大きくなっていきます。けっこう緊張感があるゲームです。
37:アーク・ノヴァ(Ark Nova)(2,749円)
動物園運営ボードゲーム。ルールはけっこう複雑ですが、大雑把にいえば、まずは1~5マスまでの大きさのヘクスタイル(囲い)を配置し、その上に動物を配置していくというものです(動物も1~5までのサイズがあって、それに合うタイルサイズでないと置けない)。
特定の種類や生息地などをそろえることで得点ボーナスを得ていったり、後援者や協会の力を借りたりなどで点数を稼いでいき、最終的に勝利点が一番多いプレイヤーの勝ち。デジタル版でも1プレイにけっこう時間がかかります。『シヴィライゼーション』シリーズとも似たようなところがあるので、そういうのが好きな人にも合うのではないかと。
38:カスカディア (Cascadia)(1,700円)
こちらも動物関係のボードゲームですが、『アーク・ノヴァ』と比べればかなりルールは簡単です。ヘクスタイルを並べていって、地形をつなげることで得点を得たり、タイルの上に動物を配置して、同じ種類の動物をつなげるなどで得点が得られます。ひとりでまったり遊ぶも良し、対戦して点数を競うも良しで、リラックスして遊ぶことが出来ます。
まとめ
Steamで遊べるおすすめボードゲーム、いかがだったでしょうか?
日本でも実物が発売されているものが多いので、デジタル版をプレイして気に入ったら、ぜひとも実物を購入して、家族や友達と遊んでみてください。
今後も気になるゲームがあれば追加していきます。